目標は高く持つべし!…?
- 森田 哲

- 2024年8月3日
- 読了時間: 3分
「目標は高く持ったほうがいい。」
よく聞く言葉です。僕もよく言います。(笑)
まぁ用は、目標を高く掲げた方が、その目標には届かなくても、その目標よりワンランク下の目標には到達できるよということなんです。
例えて言うならば、仮に泉高校に進学したいとして、泉高校目標に頑張るよりは、もう少し偏差値の高い仙台二華や、宮城第一等を目標にすると、それらには届かなくとも泉高校に安心して受かる位の学力がつくよ、ということです。
最もだと思います。
高校受験ならね。
公立高校の場合は、偏差値が高かろうが、入試問題は一律で同じなので、対策の仕方はほぼ同じです。
強いて言えば、どこの問題を捨てるかがちょっと変わってくる位。
なので、高いところを目標にして、3年生1月のみやぎ模試の結果で最終的にどこに出願するかを決めれば良いのです。その時に掲げた高い目標に届かなくても、それよりワンランク下の確実に入れるところに入れれば良いのです。
(このときの出願校の決め方については、また後日の記事で)
でも大学受験だと、そうもいかない。国公立大学でも、科目の取り方は大体同じだけど、微妙に違うところもあります。
例えば、数学なら、文系の学部に限られますが、数学はⅠAかⅡBのどちらかだけで良かったり、もしくはⅠのみでよかったり。
高崎経済大学のように、共通テストの数学の結果を利用せず、受けられる大学もあります。
理科ですと、発展2科目ではなく、発展1科目と、基礎2科目で受けられるところもあります。
科目数が増えますが、基礎というだけあって、内容はまだ簡単ですので、例えば、「化学と物理両方を対策するのはきつい」という人には向いています。
ただし、大学によっては「同一名称組み合わせ不可」となっているところもあります。例えば、化学と化学基礎と物理基礎という組み合わせは、「化学」が被っているからダメということです。
こうなると、生物基礎とか全く別の分野にしないといけなくなります。
ちなみに、山形大は、以前までは同一名称OKだったのですが、共通テスト制度が変わった今年度から、不可になってしまいました…
今年度も可なのは、宮城大、秋田大など、意外とあります。
そして、二次試験は、大学独自の問題で、科目やその数は大学様々です。
そうなってくると、どこの大学を目指すかによって対策の仕方が変わってくる部分が結構あります。
なので、目標を掲げつつも、その目標に到達できなそうだと判断した場合は、自分の今の現状に合わせて目標を変えるという臨機応変さも、必要になります。
例えば、どうしても数学で点数が取れないから、数学を使わない大学にしようとか。
昨年度、大学合格した生徒さんは、この臨機応変さを持っていたからこそ、合格できたともいえます。
目標を変える事は、決して逃げではありません。それも戦術の1つです。高校受験に比べると、多種多様性がはるかに高い大学受験だからこそ。
こういった進路アドバイスも、行っております。



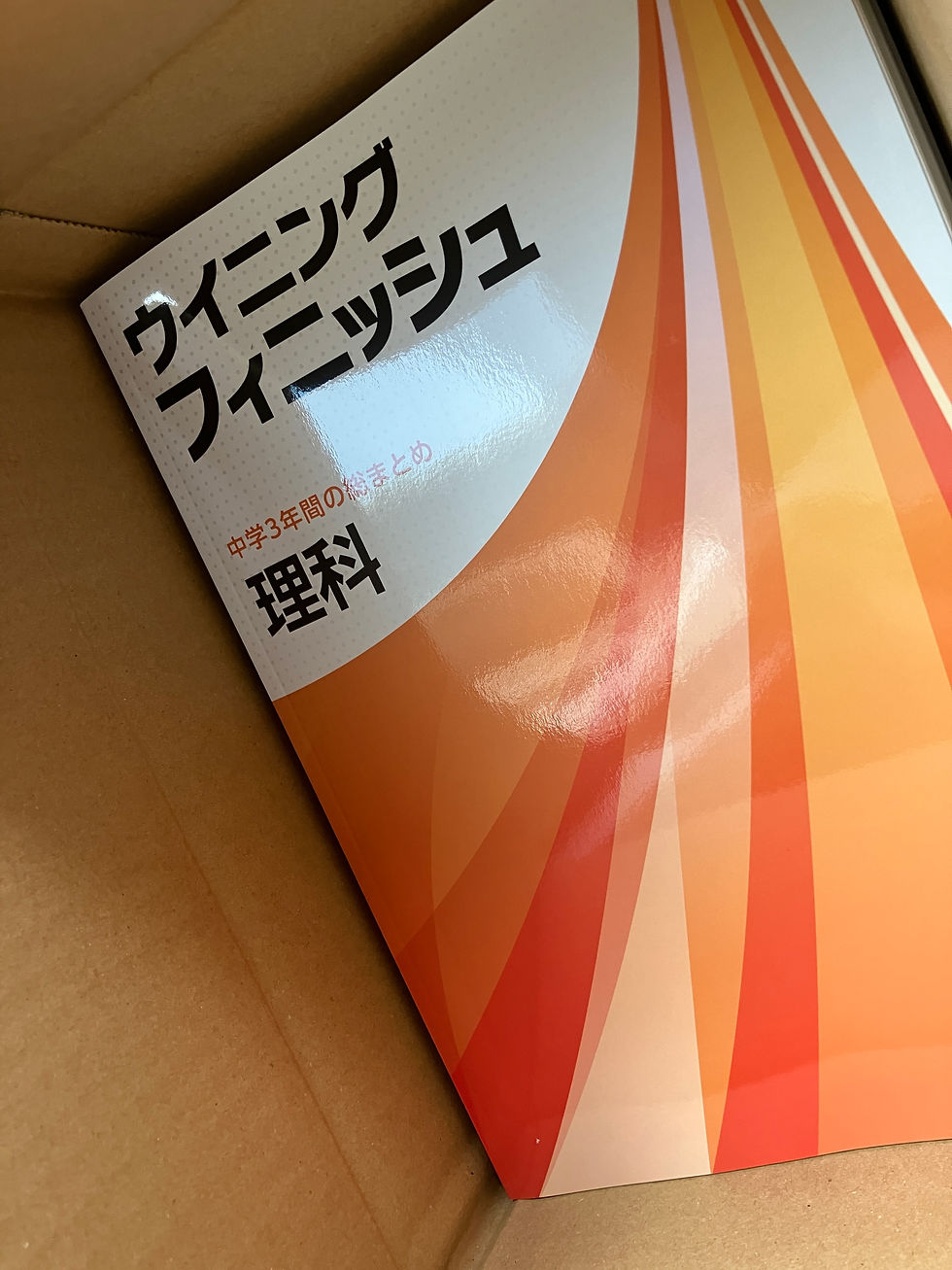
コメント